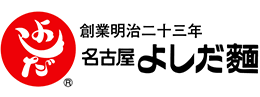きしめん辞典
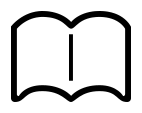
きしめんに関する
あらゆる知識をご紹介!
-
天ぷらきしめん<家庭のレシピ>

吉田麺業のメニューより「天ぷらきしめん」
上の写真は白つゆベースです。
家庭用に、赤つゆベースのめんつゆを使ったレシピをご紹介します。サクサクの食感ときしめんがよく合う天ぷらきしめん
かき揚げ、海老天でボリューム満点!
下の動画をクリックすると、天ぷらきしめんの作り方の説明が流れます。
定番のきしめんを作った後で天ぷらをのせるだけなので簡単です。
■材料(2人分)
■基本の作り方
- きしめんをパッケージに従って茹で、冷水でよく冷やし、ざるにあげます。
- 鍋にめんつゆ二人前と500mlの水を入れ温めます。
- めんをお湯の中に戻し温めた後、水気を切ってどんぶりに盛り付けます。
- 揚げたての天ぷらをのせ、めんつゆをかけます。
- 最後にお好みでゆずの皮をのせて出来上がりです。
■食べ方のポイント
- おすすめの具材は、えび、かき揚げ、海苔、なす、かぼちゃです。
- きしめんはパッケージの指定に従って茹でてから、冷水でしっかりと締めます。
このとき、茹で上がった麺は冷水に入れ、2回ほど水を替えながら手早く完全に冷ますのがポイントです。
-
きしめん<家庭のレシピ>

吉田麺業のメニューより「きしめん」
「きしめんってどうやって作るの?」
特に具材についてはよくご質問をいただきます。最も定番の作り方として、ここでは、創業明治23年の当社・吉田麺業で提供させていただいている「きしめん」を家庭用にアレンジした作り方をご紹介します。
もっちりとした平打ち麺と、ムロアジをベースにたまり醤油で仕上げたコクのあるつゆ。
老若男女に愛される名古屋の味です。下の動画をクリックすると、きしめんの作り方の説明が流れます。
■材料(2人分)
■基本の作り方
- きしめんをパッケージに従って茹で、冷水でよく冷やし、ざるにあげます。
- 鍋にめんつゆ二人前と500mlの水を入れ温めます。
- めんをお湯の中に戻し温めた後、水気を切ってどんぶりに盛り付けます。
- ホウレン草やかまぼこ、油揚げなどの具をのせ、めんつゆをかけます。
- 最後にけずりぶしをのせて出来上がりです。
■食べ方のポイント
- お好みでねぎをそえても、美味しくいただけます。
- きしめんはパッケージの指定に従って茹でてから、冷水でしっかりと締めます。
このとき、茹で上がった麺は冷水に入れ、2回ほど水を替えながら手早く完全に冷ますのがポイントです。
-
八丁味噌
-
幅広きしめん
通常でも、うどんより幅が広いのがきしめんですが、さらに上をいく「幅広」麺が、数年前からきしめんファンに注目されています。
日本農林規格(JAS)の乾麺の基準が、幅4.5ミリ以上のところ、その倍どころか10倍近い4センチ、さらには5センチのきしめんも登場しています。 -
「きしめん」と「ほうとう」の違い
武田信玄も愛した山梨の「ほうとう」。「きしめん」との最大の違いは「塩」にあり。

きしめん

ほうとう
名古屋の「きしめん」と同様に、平たく薄い麺を使う料理として山梨県の「ほうとう」があります。
「ほうとう」は山梨県を代表する郷土料理
ほうとうは、平打ちの麺をかぼちゃや芋、根菜などの野菜を中心とした具材とともに味噌仕立てのつゆで煮込んだものです。
ほうとうの歴史は古く、戦国時代には武田信玄が陣中食として食べていたという説もあります。同じ平打ち麺を使う「きしめん」と「ほうとう」ですが、その麺のつくりには大きな違いがあります。
◇最大の特徴は「塩」
「きしめん」はしっかりとしたコシを生み出すために塩を加えて生地を打ちますが、「ほうとう」の場合は塩を加えずに小麦粉と水のみで生地を打つのが基本となります。またコシを生み出すために生地を寝かせて熟成させる「きしめん」に対し、「ほうとう」は出来上がった生地をすぐに伸ばして切るのも特徴。
「ほうとう」は、打ち粉をつけたまま味噌仕立てのつゆの中で煮込むため、とろみのある仕上がりになります。◇つゆ
「きしめん」はたまり醤油や白しょうゆ等を使ったつゆで食べることが多いのに対し、「ほうとう」は味噌仕立てのつゆで煮込むのが基本。
その点では「ほうとう」は「きしめん」よりも「すいとん」や秋田の「おっきりこみ」などに近い料理といえましょう。
地元山梨の家庭では大きな鍋で「ほうとう」を煮込み、汁物として食べられることも多いそうです。名古屋の「きしめん」と山梨の「ほうとう」、どちらもそれぞれの地域に根ざした料理として今も広く愛されています。
※ほうとうの写真の出典:ほうとう歩成さまWebサイトメニューページ「黄金ほうとう」
https://www.funari.jp/menu
(2021年11月29日に利用)